
まわりの人が楽しく過ごせるように。
その思いを原動力に、
琴平町を、香川県をもっともっと元気にする。

株式会社五人百姓 池商店 28代目
池 龍太郎さん
関西学院大学経済学部 2015年3月卒業
大学卒業後、出身地である香川県にて銀行員として勤務、その後、地元・琴平町役場で行政に携わる。コロナ禍を機に、鎌倉時代から続く家業「五人百姓 池商店」を継承。店舗を100年ぶりに全面リニューアルし、伝統の加美代飴を守りながら、地域の魅力を伝える“語り部”として町の小さな観光大使を増やす取り組みにも力を注いでいる。学生時代から続ける弓道では、世界大会に出場、母校の指導にも尽力している。
- 30代
- 会社経営
- ツーリズム
金刀比羅宮の神事を支える家系に生まれて
こんぴらさんの愛称で親しまれる金刀比羅宮(ことひらぐう)は、御本宮まで785段、奥社までは1368段の石段が続く。この石段の69段目にある「五人百姓 池商店」の28代目にあたる池さんは、地域のことを愛着を持って“石段”と呼び、石段に育てられたと話す。
「金刀比羅宮の石段沿いのお店は、今、地域の課題とされている「顔の見える関係」が本当に息づいているエリアです。毎日シャッターが開き、お店が開くと自然と顔を合わせる。だからこそ、人と人との距離がとても近いのです。一人でお茶を飲むのではなく、お茶が入ったら、近所の人たちに配り合って一緒におしゃべりが始まる。学校帰りの子どもを見つけたら、お菓子を手渡してくれる。そんな温かい環境だったから、地域の人は家族のように感じています」
石段には、池商店と同様に、「五人百姓」とつく店が5軒ある。「五人百姓」とは、金刀比羅宮の御祭神にお供し、神事を支える5つの家筋のことで、ここでいう百姓は多様な職能を持つ人々のことを指す。池家を含む5つの家は金刀比羅宮と古くからの縁があり、さまざまな神事をお手伝いしてきた。

「五人百姓は、金刀比羅宮の神様にお供して琴平の土地にやってきた五家の眷属(けんぞく)の末裔です。町の人間でありながら、神様のお手伝いをする役目を担い、神様と町をつなぐ存在として、大門の内側という特別な場所で海を超えて持って帰ることのできるご利益飴・加美代飴(かみよあめ)を販売させていただいています」

五人百姓や池商店はいつ頃に誕生したかは書物によりさまざまだが、五家に正式な記録が残っているのは天皇家から書簡をいただいた1245年とのこと。そんな歴史のある門前町には、「いわゆる顔の見える関係がずっと続いています。今も、何かあったときのために、近所の家の鍵を預かったりしているんですよ」と池さんは話す。
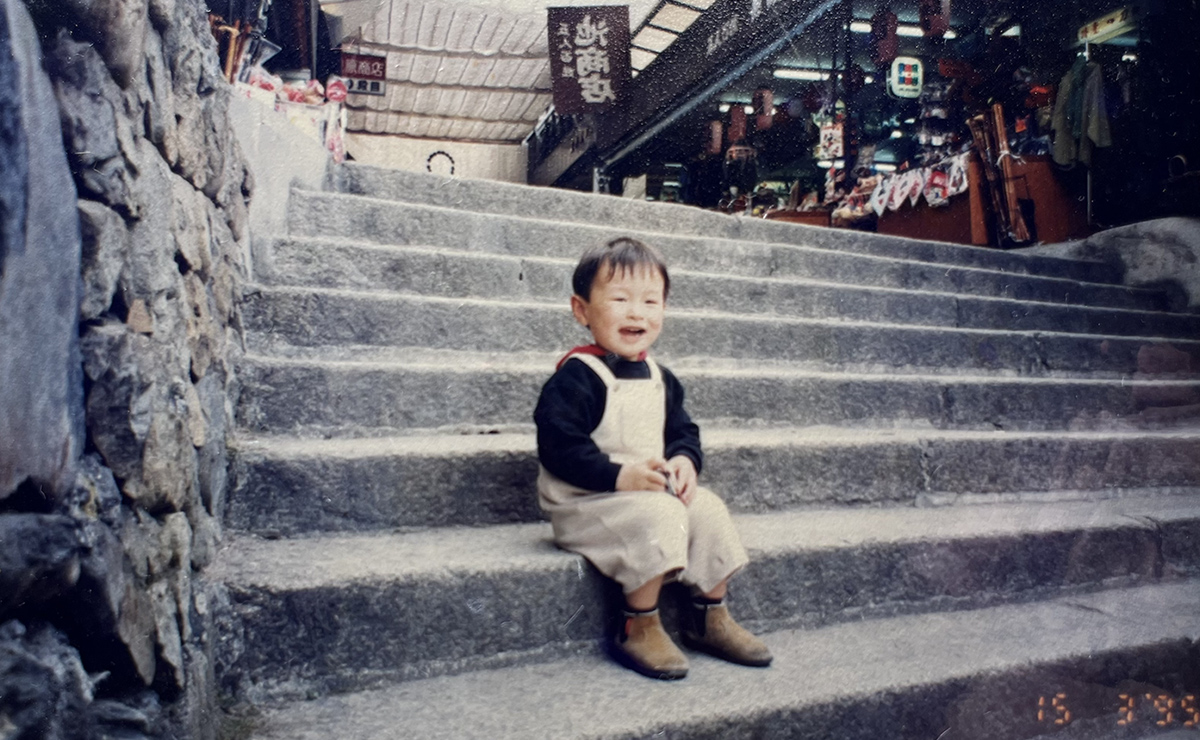
弓道で日本一を取りたいと関西学院大学へ
池さんが関西学院大学に進学したのは、弓道で日本一を取りたいとの思いからだった。関学の体育会弓道部は1912年に発足し、全国制覇も果たしたことのある名門弓道部だ。
「弓道は高校からはじめました。主将を務め、男子団体としては香川県総合体育大会で初優勝し、その高校ではじめてインターハイに出場しました。でも、インターハイでは予選敗退という結果になってしまい、不完全燃焼なまま終わってしまった。それで大学では日本一を取ろうと、関学に行こうと決めたんです」

そうして入った関学弓道部で活動を続ける中で、池さんは「必要以上の厳しさで縛るのではなく、部員全員が心から部活を誇り、日本一を取りに行けるような弓道部をつくりたい」と考えるようになった。関わったすべての部員が、最後の瞬間に自然と「この部に入ってよかった」と言葉にできる、そんなチームづくりをめざしてきた。
そのために、0から新しく部のルールをつくり直し、2学年連続で主将を務めながら、さまざまな改革に取り組んできた。全国大会で団体2位という記録も残した。池さんたちの代が引退する日、1年生が泣きながら「関学弓道部に入ってよかった」と話してくれた。本当なら彼らが思い出や経験を積み重ねて引退する日に口にするような言葉を、入部1年目で口にしてくれた。この日のことは忘れられないと、池さんは振り返る。

コロナ禍と親友の死をきっかけに家業を継ぐ
大学卒業後、池さんは地元に帰って銀行に、次いで町役場に勤めた。池さんは、ご両親がお医者さんから「子どもは難しいかもしれない」と言われるなか奇跡的に生まれたひとり息子である。両親もそれを気遣い一度も家業を継げといわなかった。ただ、五人百姓は、五家が揃って神事のお手伝いにあたる。どこかが欠ければ回らないため、家を継がなければという思いは、五家に生まれた子どもなら当然のようにあるのではないかと池さんは話す。
それでも、すぐに家業を継がなかったのは、いろいろな知識をつけたい、地域のことをもっと知りたいと思ったからだった。学生時代の卒業文集で「香川県をよくしたい」と書いていた池さん。地域のために何ができるかをつねに考えていた。町役場で勤務していた頃も、本当の地域課題を知るために、自ら自治会をまわって話を聞き、防災士の資格を取得して出前講座を開催するなど、精力的に活動してきた。若手職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、仕事を楽しみながら取り組める仕組みづくりにも挑戦。さらに、NHKの全国放送に出演し、石段を駆け上がって生中継で琴平の魅力を全国に紹介するなど、幅広い発信にも取り組んできた。

家業をいつ継承するのかは明確には決めておらず、行政でも自分のできることを全力でやろうと取り組んでいく中、そのターニングポイントになったのは2つの出来事だった。ひとつはコロナ禍だ。
「2020年5月の緊急事態宣言で、金刀比羅宮も参拝禁止になりました。参道に人が通らなくなり、石段の隙間から雑草が伸び、地域の交流がなくなったことで、近所のおじいちゃん、おばあちゃんが目に見えて弱っていったんです。これは何とかしなくてはと強く感じました」

もうひとつは、一緒にインターハイを戦った親友が心臓突然死で急死したことだった。友人の両親から連絡をもらい、そのことを知った。同級生たちと墓参りに行ったときにかけられた言葉が、池さんの背中を強く押した。
「亡くなった親友のお父さんが私たちに話しかけてくれました。『みんな、いつかやりたいと思っていることはあるかい?やれるうちにやりなさい。明日はできないかもしれない。あいつはできなかった。何をはじめるにも、今日この瞬間が一番若いのだから』と。この言葉で人生の歯車が動き始めました。本当に自分にしかできないことを全力でやろうと決意しました。そして自分の命が終わる時に再会した友人に『やりきったよ』と伝えたい。人生が動いたのは私だけではありませんでした。政治家になりたいといっていた友人はその日のうちに会社を辞めることを決めて政治家秘書になり、今はある市の議員になっています。別の友人も、香川県に帰って親の会社を継ぐ決心をしました」

家業のほか、地域の魅力を伝える活動も
コロナ禍に家業を継いだ池さんは、「老舗ががんばることで地域を元気づけたい」と、まず池商店の約100年ぶりの大規模改装に着手した。飴づくりを見学できるようにするなど、これまで紡がれてきた長い歴史とこんぴらさんや五人百姓、加美代飴のストーリーが感じられることを意識したという。「ストーリーをよいと思わなければ人は動かない。よいと思えば人は動く」といい、これに気づかせてもらった大学時代の出来事を話してくれた。
「関学に入ってすぐ、同じく県外から来た友人ができました。どこから来たの?という質問に、私はこんぴらさんの歴史や店のことを熱く語ってしまったんですね。すると、翌週会ったとき、彼は加美代飴を持っていました。『池の話を聞いたらおもしろくて答え合わせがしたくなった』と。最初の大学の休みで香川県に行くって、すごいと思うんですよ。私の話で、友人の心が動き、足を運んでくれたことが本当にうれしかったんです」

五人百姓の家に生まれた池さんにとって、桃太郎や浦島太郎などの昔話と同じように、こんぴらさんの物語を話せるのは当たり前のことだった。ただ、いくら琴平町に住んでいても全員がそうではない。そこで、池さんは「町の外に行ったときに、こんぴらさんのストーリーを話してほしい」との思いから、地元のこども園から大学生、大人にも五人百姓と町の歴史などを伝える活動をはじめた。池さんがそうであるように、地域のことをどれだけ話せるかはシビックプライドの醸成に大きく関わる。
他にも、官公庁の研修会で話したり、旅行会社と一緒に全国を巡ったりして、こんぴらさんだけでなく、香川県の歴史や文化、魅力を伝える活動を続け、香川県に来たことがない方が一歩目を踏み出したくなるような人に話したくなるストーリーをたくさん伝えている。
池さんの目的は「小さな観光大使」を増やすこと。小さな観光大使とは、琴平の町のことを外で話せる人のこと。池さん本人が「琴平の町は良いところだよ」と伝えるだけでは、「地元の人はそう言うよね」と受け取られてしまう。そうではなく、池さんの話を聞いた方が、友だちに伝えたくなったり、家族に話したくなったりと、自然に外で琴平の魅力を語ってくれること。それが地域の価値を高めていくのだと考えている。
語り部の話を聞いた人が次の語り部となり、町の魅力は拡散される。「あなたは関係人口ですよ」と言われると身構えてしまうけれど、「あなたも今日から小さな観光大使ですよ」と伝えると、たくさんの方が「よし、魅力を伝えよう」と町のことを広めてくれる。そんな広がりを、これからも大切にしていきたいと語る。
「家業を継いだ今も、町をよくしたいという思いは変わりません。銀行や町役場の仕事を通じて、いろいろな地域の人たちとふれ合い、本当の地域課題を知り、いきなり家業を継いだのではできない経験をしました。一人の地域のプレーヤーとして、ローカルの価値と可能性を伝え続けるのが私の役割だと思っています。たとえば、琴平町には公立図書館がないのですが、2017年に『まちじゅう図書館』というプロジェクトが始まり、池商店も参画しています。カフェや銀行、病院などの街角に本棚を置き、町中で本が読めるという取り組みで、地元の子どもたちがこんぴらさんの本を読みにお店に入ってきてくれます。町にないものはみんなで工夫してつくり、子どもたちも自然と町を知るきっかけになる。こうした町全体を活性化する活動は、やがてはローカルの価値につながっていくと考えているんです」

原点は地域への恩返しと「関わるすべての人に幸せになってもらいたい」という思い
金刀比羅宮は、古くから「人生に一度はこんぴら参り」といわれてきた。本来は、一生に一度は行っておきたいとの意味だが、最近では「石段がきついから一度で十分」などとネガティブな意味で使われることもあるという。池さんはそれを変えたかった。コロナ禍で琴平町は大きなピンチに直面した。これをきっかけに、町の人たちが集まって本気で話し合う作戦会議が始まった。観光地として日々忙しく、これまでなかなか腰を据えて語り合う機会がなかった町のメンバーが世代を超えて集まり、この危機をどう乗り越え、どう戦うのかを真剣に議論する場が生まれた。池さんもその一員として参加し、地域の未来に向けた本気の議論を重ねてきた。そして今、琴平町で「人生に一度」ではなく「人生に何度でも訪れたくなる町へ」を新たな地域テーマに掲げてみんなで仕掛けづくりに取り組んでいる。
「琴平町だけで使われる“山上山下(さんじょうさんげ)”という言葉があります。山の上とは金刀比羅宮のこと。山の下は、その下の門前町。どちらか一方ではなく、山上も山下も一緒になって両方の価値をあげていくことが大切だと昔から言われ続けてきました。そこで、山上山下一体となって金刀比羅宮の縁日である10日を盛り上げようと、『こんぴら十帖』プロジェクトを立ち上げました。さまざまなお店が10日限定のメニューを月替わりで提供することで、10日に何度でも訪れたくなるように、思い出してもらえるように活動しています」

琴平町の面積は8.47平方キロメートルしかない日本で1番小さな香川県の2番目に小さな町である。町が発展するには、金刀比羅宮、民間企業、行政の連携が欠かせない。池さんは、銀行という民間企業と行政を経験し、五人百姓として金刀比羅宮とも付き合いがある。「だからこそ架け橋になっていきたい」と意気込みを語った。
学生時代でも仕事でも、池さんを動かすのは「関わるすべての人を幸せにしたい」という思いだ。それは“Mastery for Service”の精神にもつながる。
「思い返せば、弓道部をよくしたいというのも自分のためではありませんでした。部を変えるには時間もかかるし労力も必要です。でも、自分がどうこうではなく、同期や後輩たち、関わるすべての部員が本当に良かったと思える環境をつくること。自分がこの場所にいて関わったからこそできることがあるなら努力を積み重ねたいと思ったんです。今でも“Mastery for Service”という言葉が好きで、自分の支えであり、原動力にもなっています」

池さんは、自分のまわりの人たちが楽しく過ごすところを見ること、そして次の世代にも伝えたくなるほど誇れる場所や環境をつくることが、自分にとっての豊かな人生だと話す。
「先祖から受け取ったバトンを手に、今、走っているのが自分なのだという感覚があります。コロナ禍を経て、この町は地元の方も、移住してきた方も、奇跡的なメンバーがそろい、連携しながら動き始めました。780年以上続く家に生まれましたが、私は今の琴平町が、歴史上もっともおもしろい時代だと本気で思っています。この時代に生まれさせてくれたことに、心から感謝しています。自分の持つバトンを受け取る価値のある大きなものに、最大限していく中で、常に自分にできることを精一杯やり抜き、琴平という町の名が世界に轟き、次の世代が『この町に生まれてよかった』と思える未来をつくりたい。その目標に向かって、これからも全力で挑み続けたいと思っています」
-
38

